
 |
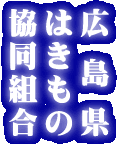
|
|
| はきもの産業のふるさと「松永」。 それは下駄から始まりました。 明治11年頃、塩田のひろがる松永の地で、下駄小売商丸山茂助が塩を焚く木材に目をつけ、桐に似た安い雑木(アブラ木)で下駄の製造を始めました。 明治40年頃、全国に先がけ次々と下駄製造の機械化が行われ、大量生産の基礎が作られました。 大正、昭和の初期の不況にも耐えぬいて、昭和10年頃には仕上機械の導入により全工程機械化に成功し、組合員も11社ありました。以来、第2次世界大戦を経て組合員数も150社を超え、全国の需要をまかないました。 昭和30年には下駄の生産足数はピークをむかえ、同じ頃木ヒールが、昭和30年代中頃からサンダルとスリッパが、各々に下駄製造のノウハウを生かし、はきもの全体への展開を図りスタートをきりました。 こうして「松永」は昭和40年代には、はきものの総合産地として拡大を進め、昭和50年代の消費者の生活、 文化の多様化個性化にすばやく対応し、確固たる地位を築き上げました。「松永」が「はきものの里」といわれるゆえんです。「松永」の産業の基礎を築いた先人たちに学んだ経験を生かし、「はきもの産業」を更に発展させるべく努力することが、私達に課されたつとめだと思います。 |