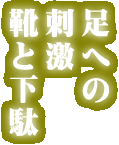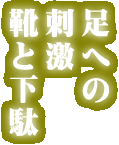|
1)裸足歩行に近い下駄の形状は? -足底圧による検討- |
 |
| |
Fスキャンという足底圧を測定する機器を用い、裸足及び履き物を履いたときの足底圧を計測しました。青い色は圧が低い、赤色は圧が高いことを示しています。赤い線は足底圧中心の推移を示しています。 |
|
 |
|
 |
| |
裸足歩行では最初に踵に体重がかかり、足の少し外側を通り、踏み返しの際は趾先部までよく体重がかかっています。
|
|
(中には、後に述べる靴歩行のようなパターンで歩く方もおられます) |
|
|
| |
|
|
| |
最初に踵に体重がかかり、足の少し外側を通るところまでは裸足歩行とほぼ同様ですが、多くの人において踏み返しが弱く、趾先部まではあまり体重がかからない傾向がみられました。
|
|
裸足歩行と異なり、足の裏全体で荷重するため足部にかかる圧は減少し、赤色はほとんどないことが特徴です。 |
|
|
| |
|
|
| |
●下駄の底は、どのような形状が良いか?
| ● |
下駄の上面は、どのような形状が良いか? |
| |
(昔ながらのフラットなものが良いのか、革靴の中敷きの傾斜に近いカーブが良いのか?) |
●踵はどのくらい高くするのが良いか?
|
|
以上の3つの点について検討し、様々な条件での実験の結果、"裸足歩行とほぼ同様な踏み返しを伴ったパターン"を容易に再現して歩ける下駄の形状は、"下駄の底には踏み返しが容易になるようなカーブをつけ、踵を前足部よりわずかに高くし、下駄の上面をフラットにした下駄"ということがわかりました。 |
|
|
 |