 |
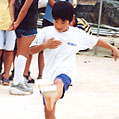 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
| この度、福山商工会議所では、経済産業省と福山市の支援を受けた地域振興活性化事業として、松永の伝統産業「下駄」の振興に取り組んでまいりました。この事業によって、英知を結集し検討を重ねる機会を得て、21世紀を生きる私たちの足元に、再び下駄の感触を取り戻すことが出来ることを願っております。 「下駄は健康に良い」・「湿度の高い日本の風土に適している」と分かっていても、なかなか下駄離れをくい止めることは出来ませんでした。そこで下駄の良さを科学的に検証することから始めました。次に、下駄をはいたことのない小学生に下駄に馴染んでもらおうと、松永地区の小学生400名余に下駄に好きな絵を描いてもらい、はいてもらうことにしました。 「下駄とばし」は昔のこどもにとっては懐かしい遊びです。これを現代に生かすべく、ルールを作り下駄の規格を定めて、全国へ発信しようとしています。年齢を問わず身近にあるニュースポーツとして楽しんでいただきたいものです。 過去1000年以上の歴史をもち、改良を加えられて来た下駄です。大きさも限られているはきものに、「アジアンテイスト」・「和風」というスパイスをきかせて世界に問うのが、「新時代の下駄」です。こうして、現代社会にマッチした下駄が生まれました。 「健康によい下駄」・「下駄とばし用下駄」そして「新時代の下駄」は、すべてインターネットを通じて世界中から注文を受けられるようになっています。足を包み込む靴に対して開放性のはきものである下駄は、それをはくことによって足だけでなく心まで開放してくれることでしょう。さわやかな自然の感触を是非楽しんで下さい。
|
| 福山市松永地域(旧松永市域)は、下駄から始まったはきもの産業のまちです。 下駄の製造が開始された明治11年から国民の履物を支える産業として栄え、昭和30年のピーク時には5,600万足を生産し、名実ともに下駄の街として盛況を来たしました。明治後期からの機械化により、大量生産の基盤をつくり、大きな歴史の変動期にも、全国の需要をまかなっていましたが、生活様式の変化に伴って生産量は下降傾向となり、事業の転換を余儀なくされた製造業者は、ケミカルシューズ、サンダル、スリッパの製造、木ヒール加工等へと下駄製造のノウハウを活かしながら、はきもの全体への展開を図ってきました。 履物関連業者で組織する広島県はきもの協同組合では、地域ぐるみのイベントへの参加や新作展示会の開催など、地場産業の振興に努めており、福山商工会議所においても、下駄を中心としたはきもの産業が及ぼす地域経済への影響を鑑み、履物製造業者の経営基盤の強化を図りつつ地域振興の推進をしているところです。 しかし、消費者の履物に対する価値観の変化や、海外からの安価な製品の流入等により、需要の減退は著しく、後継者不足等も重なって、はきもの産業は衰退の一途を辿っています。こうした中で、現代の消費者の需要に対応できる新商品の開発及び販売方法等を見直し、基盤の確立を図りながら後継者を発掘することにより、はきもの産業の歴史と伝統を後世に継承していくことが求められています。 松永地域が、趣味として履く下駄から実用的な履物まで幅広い履物の産地として、より活性化していくものと期待して、この事業を実施しました。 |
| 1.新商品の開発 2.インターネットによる下駄の台及び鼻緒の組み合わせ販売システムの構築 3.日本はきもの博物館を中心とした「はきもの」のシンポジウム及びイベントの開催 |