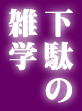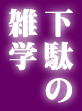古墳時代には限られた遺跡から、ごく少量ずつしか出土せず、下駄の使用はかなり限定されたものだったと考えられるが、しだいに一つの遺跡からの出土量が多くなっていく。なかでも、滋賀県大津市の湖西線関係遺跡では、古墳終末から飛鳥にかかる時期の下駄が21点出土している。この遺跡には渡来人の群集墳が多数あり、下駄の使用との関連性もうかがわせる。この遺跡から出土する下駄は、台長28〜16センチと使用者の幅の広がりを推測させるものであり、前の緒穴が左右に片寄ってあけられている。
この前緒穴の片寄り、つまり左右の違いのある下駄は、現在でも日本以外の使用地にはみられることである。いいかえれば、前緒穴が台中央にあけられるのは非常に日本的な特徴なのである。この日本特有の形が出現するのは9世紀前半、平安時代初期のことである。
奈良時代の都だった平城京跡からはこの時期の下駄が80点以上出土している。台はほぼ長円形にととのってきており、長さも18〜24センチのものが多くなる。そして前緒穴が中央に位置するものが約80パーセントをしめている。年齢や性別を問わず使用されるようになっていくことがうかがえる。
武家社会となる鎌倉・室町時代には、武士が鼻緒のついたはきもの−草鞋・草履−を履くようになり、下駄の使用も増えていく。鎌倉市市街地遺跡・広島県草戸千軒町遺跡(写真6)・福岡県大宰府跡など、非常に多量の下駄が出土する遺跡が多くなり、台の形にも相似性がみられる。長円形の台は左右対称になり、緒穴が錐ではなく焼火箸(鉄棒)であけられるなど、大量生産への道筋、地域を越えた技術の伝播がうかがえる。
この時期の大きな変化は、これまでの一木二枚歯の連歯下駄に、台と歯を別材で作って差し込む差歯下駄が加わることである。中世になって連歯下駄も歯が相当高いものになっていた。おそらくは、その高下駄を作るための材を有効利用するために考えられたものと推測できる。
|