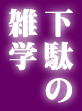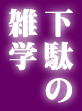大正モダニズムを経て昭和にいたると、日本の服飾も西欧のファッションに並ぶようになる。その中で、着物とそれに合わせる下駄や草履も、伝統技術の粋を集めて「最後の華やぎ」ともいえる姿を残している。
下駄では、台の漆塗りに格式のある「金蒔絵」(写真12・13・14・15)が取り入れられ、鼻緒の素材のビロード・錦織・縮緬なども織りや色彩が多彩になる。柄も松や鶴を描いた古典的なものからストライプや矢羽をモダンにアレンジしたものまで、和と洋を融合した華やかさがみられる。これは「洋装」の普及に大きく影響されたものであり、それは台の形にも現れ「天反り」(写真16・17)という斜めの台を生んでいる。このスタイルは、昭和4年に飛来したドイツの飛行船ツェッペリン号の姿になぞらえて、「流線型」と呼ばれて、若い女性の憧れの的になったという。
その後に続く戦争による物資不足の中で下駄も統制品となり、仕上げの途上のような「戦時下駄」(写真18)さえ配給でしか手にはいらない状況になった。しかし、戦争の終結とともに下駄産業もめざましく復興していく。
松永でも、運輸手段がつかず県内産の松を使ったが、その重い下駄さえ飛ぶように売れたという。昭和27年頃からはベイドロ(北米産泥柳)に落ち着き、開発が進む化学塗料や接着剤による装飾加工が多種にわたって工夫されていく。そうして、30年には5600万足という生産量を達成している。しかし、それをピークに需要は急激に落ち込み、5年後には4000万足を切り、10年後には2000万足に達しないという状況をむかえている。
|